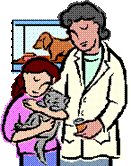 |
■ 医療的ケアとは、治療を目的とするのではなく、健康状態の 維持・改善のために必要とする医療的な行為を、医師の指導 の下で保護者が日常的に家庭で行っている行為をいいます。 内容は、痰の吸引、導尿、経管栄養などです。 ■ これらの医療的行為を主治医の指導の下、学校内で学校看護 師が行っています。この医療的ケアにより、障がいの重い児童・ 生徒が学習への参加が可能になったり、いろいろな活動に参加 する機会が広がることで社会性が育ったりしています。 ■ これまで保護者は、自分のお子さんの医療的ケアを実施する ために学校で待機しなければなりませんでした。しかし、学校 看護師が配置され、これまでの負担がかなり軽減されることと なりました。 |
 |
■ 当校では、平成16年度文部科学省「養護学校における医療 的ケアに関するモデル事業」、平成17年度文部科学省「盲・ 聾・養護学校における医療的ケア実施体制整備事業」の実施 校として学校看護師(非常勤)2人の配置により取組を進 めてきました。 ■ 平成19年度からは、学校看護師3人体制となり、より安心 安全なケアができるように努めています。 ■ 現在、対象児童生徒が常時10人を超え、県内で最も多くの 医療的ケアを実施しています。(対象児の割合は約12%) ■ 安全かつ効率的なケアを行うため、「ケアルーム」を中心に して実施していましたが、平成19年度からは、教室でも痰の 吸引や水分注入などのケアを開始しています。 ■ 平成18年度からは、学校看護師との連携の下に行う教員 による補助的ケア(咽頭前の痰の吸引、経管栄養の際の補助) を実施しています。 |
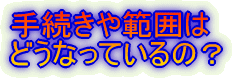 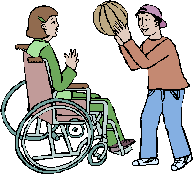 |
■ 実施を希望する場合は、所定の用紙や手続きに従い、主治医か らの指示書、校内の医療的ケア検討委員会での協議などが必要 となります。 ≪手続きの主な流れ≫ 保護者の申請→医療的ケア検討委員会→医師の指示書→ケア開始 ※教員による補助的ケアについては、校外で行う基礎研修と 校内で個別に行う応用研修(主治医の下での実技も含む)が必要 です。 ■ 校内マニュアルの規程に基づき諸条件が整っている場合には、校 外学習時に学校看護師が同行することができます。ただし、全ての校 外学習に同行することはできませんので、必要に応じて保護者の方か らのご協力をお願いしています。 |
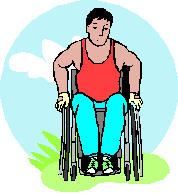 |
■ これまで、学校に長くいることができなかったお子さんが、 学校看護師から医療的ケアを実施してもらうことで1日学校 で過ごすことができ、いろいろな学習に参加したり、たくさ んの刺激を受けたりして表情も豊かになっています。 ■ 導尿のお子さんが、学校看護師の指導を受けながら担任の 先生の協力の下、1人で導尿ができるようになりました。この お陰でいろいろな所に出かけられるようになり、生活の場が 広がりました。 ■ 医療的ケアは、子どもたちの学習権を保証するだけでなく、 一人一人の自立へ向けた教育の場でもあります。 |

